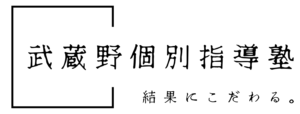総合型選抜・AO・公募推薦・自己推薦等のための小論文講座(2)
武蔵野個別指導塾の総合型選抜対策:課題文要約の極意と小論文で差をつける方法
1. 総合型選抜における要約力の位置づけ
総合型選抜(旧AO入試)では、課題文の要約が小論文の第一ステップとして非常に重視されます。要約の精度が低ければ、その後の論点整理や主張の展開すべてがずれてしまい、合格から遠ざかってしまうのです。武蔵野個別指導塾では、まず「著者の主張を一つに絞り込み、それを正確に表現する力」を徹底的に鍛えます。
小論文で与えられる課題文は、評論文や社会問題に関する論考が中心であり、字数も6000字から1万字程度と長文になる場合があります。そのため、速読力と要点把握力が欠かせません。著者の主張は通常一つに集約されますが、その一つを読み誤れば全体の構成が崩れ、採点者から低評価を受ける可能性が高くなります。
2. 要約の基本プロセス:削ぎ落としと抽出
要約の第一歩は、課題文全体を読み、「筆者が何を一番言いたいのか」を探し出すことです。武蔵野個別指導塾では「木の幹と枝葉」の比喩を用いて指導します。すなわち、木の幹が著者の主張であり、具体例や補足説明は枝葉です。要約では枝葉を大胆に削ぎ落とし、幹の部分を残すことが求められます。
例えば、環境問題を論じた課題文であれば、著者が繰り返し述べているのは「持続可能な社会に向けて再生可能エネルギーの導入が不可欠である」という一点である可能性が高い。そこに至る具体例(各国の政策比較や統計データ)は、要約時には省略または短い言及にとどめ、「結局何を主張しているのか」を軸にまとめます。
3. 誤解を避けるための注意点
多くの受験生が陥る失敗は、課題文の一部を誇張して取り上げたり、著者の意図を自分の解釈にすり替えてしまうことです。総合型選抜の小論文では、まず「著者の主張を忠実に再現する」ことが前提条件です。
武蔵野個別指導塾の添削指導では、次のような観点から要約を点検します:
◉ 主張が複数になっていないか
◉ 余計な感想や解釈が入り込んでいないか
◉ 反論や補足部分を、著者の主張と混同していないか
◉ 指定字数(300~400字程度)に収まっているか
この段階で正確性を担保することが、次に続く「自分の主張展開」への布石になります。
4. 要約と反論の関係
要約は単なる縮小作業ではなく、次の議論を成立させるための土台でもあります。小論文の流れはおおむね「課題文要約 → 論点整理 → 自分の主張 → 反論 → 再反論 → 結論」と展開します。要約を誤れば、その後の反論・再反論も空中戦のようになり、説得力を欠いてしまうのです。
そこで武蔵野個別指導塾では、「要約時点で反論の芽を見つける」練習を導入しています。つまり、著者の主張を一文でまとめたら、そこに対して「どのような異論が考えられるか」をセットで意識するのです。これにより、要約と主張展開が論理的につながる文章を作ることができます。
5. 繰り返しと類似表現の活用
小論文の要約や主張展開では、言葉の繰り返しと類似表現が効果的な武器となります。これは単なる反復ではなく、「同じ内容を異なる言い回しで提示すること」によって、読み手に印象を残す方法です。
例えば「教育格差の是正が必要だ」という主張を、「学力の機会均等を図ることが社会全体の安定につながる」と言い換える。このように表現を変えることで、同じ主張が複数の角度から補強されます。ただし、無意味な繰り返しは逆効果になるため、「強調」と「冗長」の境界を見極めることが重要です。
6. プレップ法を応用した要約のテクニック
要約や小論文の構成で役立つのが、PREP法(Point-Reason-Example-Point)です。これは「主張 → 理由 → 具体例 → 再主張」という流れで文章を組み立てる手法です。
武蔵野個別指導塾では、この手法を課題文要約にも応用しています。
-
Point(主張):著者の意見を一文にまとめる
-
Reason(理由):その根拠を簡潔に付け加える
-
Example(具体例):課題文で触れられている代表的な事例を1つ選ぶ
-
Point(再主張):再び簡潔に要約して締める
こうすることで、短い字数でも筋の通った要約文を仕上げることができ、採点者に「理解力がある」と高く評価されやすくなります。
7. 実践例:300字要約の演習
たとえば次のような6000文字程度の課題文を考えます。
「現代社会において、利便性は私たちの生活に欠かせない価値となっている。交通網の発達やデジタル技術の浸透によって、かつては数時間を要した作業が数分で終わるようになり、物理的な距離や時間の制約も大幅に縮小された。たとえば、オンラインショッピングやフードデリバリーは、自宅にいながら多様な商品やサービスを享受できる環境を整えている。こうした利便性の追求は、効率性や快適さを実現し、人々に新しい価値を提供してきたことは疑いようがない。
しかし同時に、利便性の追求は必ずしも人間にとって良い影響ばかりをもたらしているわけではない。むしろ、過度に便利になった生活は、創造性や身体的・精神的な健康を損なう危険性をはらんでいる。たとえば、徒歩や自転車での移動が公共交通機関や自家用車に置き換えられ、さらに近年では宅配サービスの拡大によって外出の機会が減少した結果、運動不足や生活習慣病のリスクが高まっていることは広く指摘されている。また、インターネット検索や生成AIの普及によって、情報は瞬時に入手できるようになったが、同時に「自分で調べ、考え、試行錯誤する」という知的プロセスが軽視されつつある。利便性の過度な浸透は、人間本来の学習能力や探究心を弱める要因ともなり得るのである。
このように考えると、「不便」は単なる不自由ではなく、むしろ人間にとって積極的な意味を持つ場合があると言える。不便さは、工夫を生み出す契機であり、また偶然の出会いや発見を導く要素ともなる。たとえば、駅から自宅までを歩いて帰ることで、普段は気づかなかった新しい店や地域の景色を発見することがある。このような「セレンディピティ」と呼ばれる偶然の出会いは、利便性だけを追求する生活の中では得られにくい。さらに、不便な状況は人間の問題解決能力を刺激する。電車が止まったときに代替ルートを探す、停電時にキャンドルを用いて過ごすといった経験は、創造性を働かせる貴重な場面である。
また、不便は健康の観点からも価値を持つ。エレベーターではなく階段を使う、車ではなく自転車に乗る、家電に頼らず家事をこなすといった行為は、結果的に身体の鍛錬となり、生活習慣病の予防にもつながる。こうした不便さの中にこそ、人間の身体性や生活のリズムが取り戻される可能性がある。現代の快適さに慣れ切った私たちにとって、不便は時に煩わしい存在であるが、それは同時に、より健康的で充実した生活への入口でもあるのだ。
もちろん、不便を肯定することは利便性を否定することと同義ではない。医療や災害対応における技術の進歩が命を救ってきた事実を無視することはできない。利便性は社会の発展を支える不可欠な要素である。しかし、利便性だけを追求し続ければ、私たちは「自ら考え、工夫する機会」を失い、人間本来の力を発揮できなくなる恐れがある。したがって重要なのは、利便性と不便さの双方を生活に取り入れ、そのバランスを取ることである。
結局のところ、不便は不自由ではない。むしろそれは、人間が創造性を発揮し、健康を保ち、新しい価値を見出すための土壌である。不便さを受け入れる姿勢を持つことこそが、利便性に依存しすぎた現代社会において、私たちが忘れかけている大切な知恵なのではないだろうか。」
これを要約すると:
要約例(約300字)
現代社会では利便性が優先されがちだが、不便さは人間に新しい発見や出会いをもたらし、創造性や健康を育む要素でもある。利便性と不便さは対立するものではなく、不便さの中にこそ新しい価値が潜んでいる。著者は、不便を受け入れる姿勢が人間の成長に必要であると主張している。
このように、余計な装飾や例示は省き、著者の主張を一点に絞ることが要約の基本です。
8. 武蔵野個別指導塾での要約指導の特徴
武蔵野個別指導塾では、以下のような方法で要約力を鍛えています:
-
段階的演習:最初は1000字程度の短文から始め、最終的に1万字級の評論文要約へとステップアップ。
-
添削指導:東大・一橋・早慶の大学院生講師が、一人ひとりの答案を丁寧に添削し、主張の抽出の仕方や冗長な部分の削り方を指導。
-
反論の芽探しワーク:要約後に「この主張に対する異論は何か?」を考えさせ、議論への発展力を育成。
-
時間管理訓練:90分試験では20分、60分試験では15分を要約に割り当てるなど、実戦的な時間配分を徹底。
これらにより、生徒は「ただ短くする要約」ではなく、**「次につながる要約」**を実践できるようになります。
9. 総合型選抜小論文で差がつくポイント
小論文における要約は、単なる作業ではなく「評価基準の半分を占める」と言っても過言ではありません。採点者は、受験生が著者の意図を正確に理解できているかを要約部分で判断します。ここで躓くと、どれだけ自分の主張が良くても、説得力を持った文章として評価されません。
だからこそ、武蔵野個別指導塾の総合型選抜対策では、要約の精度を徹底的に鍛えるのです。
10. 結論:要約力は合格への入口
総合型選抜の小論文対策において、要約力は単なる基礎ではなく合格への入口です。著者の主張を一つに絞り、無駄を削ぎ落とし、論点を整理したうえで反論・再反論へとつなげる。この一連の流れを習得すれば、立教大学・明治大学・青山学院大学・中央大学・慶應義塾大学などの難関大学の小論文試験においても、他の受験生と大きな差をつけることができます。
武蔵野個別指導塾では、課題文要約から志望理由書・面接対策まで一貫した指導を行い、受験生が「自分の意見を論理的に表現できる力」を伸ばします。小論文で確実に結果を出したい方は、ぜひ当塾の体験授業で実際の指導を体感してください。